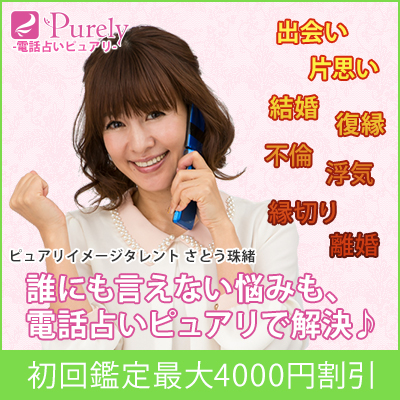九星気学について
九星気学の発祥は古代中国にまで遡ります。
古き時代から現代まで伝えられてきたということは、世代や地域を超えて支持され続けてきたということでもありますし、他の占術と同じように、様々な解釈が加えられ、多くの亜流が生まれているということも意味するでしょう。
九星気学を占術や開運法と考えている人もいれば、単なる「術」や「方法」ではなく、「学」という言葉がつくことから学問だと考えている人もいるようです。
占術、開運法、学問の違いを整理し、九星気学の本来の意義を明らかにすることは、残念ながら筆者の力量を超えています。
九星気学には、生年月日に合わせて9種類の「気」があります。
よく見かけるのでご存知の方も多いと思いますが、並べて簡単に確認しておきますと、
「一白水星(いっぱくすいせい)」、「二黒土星(じこくどせい)」、「三碧木星(さんぺきもくせい)」、「四緑木星(しろくもくせい)」、「五黄土星(ごおうどせい)」、「六白金星(ろっぱくきんせい)」、「七赤金星(しちせききんせい)」、「八白土星(はっぱくどせい)」、「九紫火星(きゅうしかせい)」の9種類があります。

「気」とはその人に備わっている性質です。
「九星」とあり、各種類の末尾にも「星」とついていますが、これは「気」を意味するのであって、天体(惑星)を指しているわけではないそうです。
1文字目の「数字」は「時間」を、2文字目の「色」は「空間」を、3文字目の「木火土金水」は万物の根源と言われる「五元素」を、意味しています。
多少強引な解釈かもしれませんが、人はそれぞれ、生年月日に応じて、「時間+空間+元素」の「気(性質)」を備えているということです。
このような考え方は、西洋占星術に対する批判と同じような批判、例えば、「人間をたったの9種類(西洋占星術の場合は12種類)に分類するのは大雑把すぎる」とか「生年月日が同じ人は同じ運勢や性質になってしまうじゃないか」とか、そのような批判を浴びるかもしれません。
しかし、このような批判は正確ではありません。
西洋占星術もそうですが、九星気学においても、一般的に知られている分類はわかりやすいように省略されたものにすぎないからです。
大きく分類すれば9種類しかなくても、本格的に鑑定する場合にはもっと細かく分類されています。
そのため、たとえ生年月日が同じでも、まったく同じ運勢や性質にはなりません。
では、詳しく鑑定する場合、具体的にどのような分類がなされ、どのような性質が明らかになり、何をすれば運勢が開けるのでしょうか。
この続きを知りたい方は、九星気学を得意とするプロの占い師に鑑定してもらってみてください。
私たちがイメージしている「占い」は、プロの占い師たちからすれば、占い全体のごく一部にすぎないようです。
本物を知るにはプロの力を見るのが一番の近道です。
九星気学の印象
九星気学は風水と一緒かなと思っていたんですけど、調べてみたら別の物みたいですね。
風水は良い方角に環境を整えることで運が開き、九星気学は良い方向に自分自身が向かうことで運が開くそうです。
いつもお世話になっている占い師さんに引っ越しをしようという意志を話の流れで伝えた所、たまたまその占い師さんが九星気学もできる方だったので私の運気がアップする方角を教えて頂きました。
その占い師さんが鑑定した方向は、私がまさに住みたいと思っていた街がある方向でした。
こんな偶然もあるのですね。
引っ越すのが楽しみになり、物件を色々と見て回りました。
占いは霊視とタロットしか経験がなかったのですが、九星気学というのも新たに知る事ができましたし、私の占いに対する知識も広がった気がします。
この九星気学を結婚した時の住まいの場所などに利用したら素敵な家庭が築けそうだなと思いました。
その為にはまずはお相手探し。
それの第一歩として、引っ越しの地を九星気学の鑑定で出た良い方角に。

先月その地に引っ越したんですけど、それから男性との出逢いが増えるようになった気がします。
その中で気になる人もできました。
これも九星気学の影響なのでしょうか…。
不思議ですね、占いって。
でもなんでもかんでも信じるのはよくない気がするので、当たる物は信じて、微妙なものは流す事にしています。
今のところは大半が合っています。
お世話になっている占い師さんによると、私が気になっている男性と近いうちに進展があるそうで、今から身構えてしまっています。
自分磨きに没頭したり、事前準備を色々と…。
九星気学の良い方角に旅行に行くのも良いみたいなので、今度の休みに日帰り旅行にでも行こうと思っています。
もうこうなったらとことんって感じですね。
九星気学は色々と奥深そうなので、これから自分でも色々と調べてみようかなと思い始めました。
友達とも楽しめそうですよね。